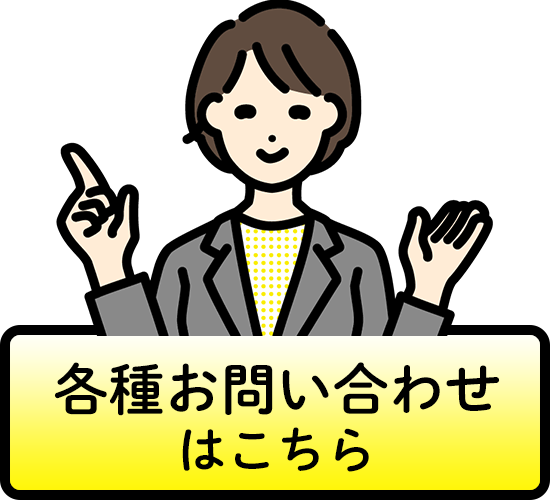一歳半 発達障害のサインとは?しゃべらない・指さししない行動を解説
1歳半ごろになると、多くの子どもたちは少しずつ言葉を覚え、身近なものを指さして伝えようとしたり、周囲と関わろうとする行動が見られるようになります。そんな中で、「まだしゃべらない」「指さしをしない」といった様子に、不安を感じる保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん、発達には個人差があり、一概に「できない=問題」と判断することはできません。しかし、発達障害のサインが早期に見られるケースもあるため、気になる行動を見逃さずに観察することがとても大切です。
この記事では、「一歳半 発達障害 サイン」というテーマで、特に多く見られる「しゃべらない」「指さしをしない」といった行動に着目しながら、どのような特徴があるのか、また発達の個性との違い、相談すべきタイミングや家庭でできるサポート方法について詳しく解説していきます。
「今のこの様子って普通なの?」「どこに相談すればいい?」という不安を感じている方に向けて、わかりやすく、安心できる内容をお届けします。小さなサインに気づき、お子さんの可能性を広げる第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。
1. 一歳半で見られる発達の特徴を知ろう
一般的な1歳半児の成長の目安とは?
1歳半ごろの子どもたちは、急激に成長が進む時期です。たとえば、歩けるようになったり、言葉が少しずつ出てきたり、「イヤイヤ」と自己主張が始まる子も増えてきます。こうした変化は、心や体の発達が活発になっているサインです。
また、この時期の子どもは、周囲の大人と関わりながら「伝える力」や「受け取る力」を少しずつ育てていきます。たとえば、何かを見つけて指をさす、絵本を一緒に読むといった行動は、コミュニケーションの土台となる大切なスキルです。家庭でのやりとりの中で、笑顔や声かけに反応するなど、目に見えにくいけれど確実な成長の一歩がたくさんあります。
一般的な発達の目安としては、「意味のある単語が1~2語程度出る」「指さしで意思を伝える」「呼びかけに振り向く」などがありますが、これはあくまで“参考値”にすぎません。
成長には個人差があることを理解しよう
子どもはそれぞれ違ったリズムで育っていきます。言葉が得意な子もいれば、運動が先に伸びる子もいます。「同じ月齢の子より言葉が少ない」「おとなしくて指さしをしない」からといって、すぐに発達障害とは限りません。
保護者としては、「他の子はできているのに…」とつい比較してしまう気持ちもあります。でも、“違い=問題”ではありません。子どもがどんなふうに過ごしているか、何に興味を持っているかをていねいに見ていくことが、成長を見守る大切な視点になります。
たとえば、言葉は少なくても表情が豊かだったり、身ぶり手ぶりでしっかり意思を伝えていたりする子もいます。こうした場合は、発達の特性を理解しながらその子らしさに合った関わり方を探っていくことが必要です。
1歳半健診でチェックされる主な項目
日本では多くの地域で、1歳半健診が実施されています。この健診は、身体面だけでなく、発達面のチェックも含まれています。以下のような項目が確認されることが多いです。
- 視線が合うか、呼びかけに反応するか
- 簡単な言葉を話すか
- 指さしを使って物を示すか
- 積み木などで遊べるか
- 保護者の話を理解している様子があるか
この健診は、子どもの様子を知る大切なきっかけです。同時に、保護者の不安や疑問を相談できる「支援の入り口」でもあります。「ちょっと気になるけど様子見でいいのかな?」と思ったら、積極的に相談してみましょう。
2. 一歳半 発達障害 サインの具体例
目が合わない・指差ししない行動の意味
目が合わない、指さしをしないといった行動は、発達障害、特に自閉スペクトラム症(ASD)のサインとして紹介されることがあります。しかし、必ずしもこれが即「障害」を意味するわけではありません。
発達の途中段階で一時的に見られることもありますし、環境や関わり方の影響が大きいケースもあります。ただ、こうした行動が続く場合は、「共同注意」の形成が難しい可能性があると考えられます。
共同注意とは、「同じものを見て、同じことに興味を向ける力」です。これは、言葉や社会性の発達に深く関係しており、「見て!」と指さして大人の注意を引く行動は、人とつながろうとする意思表示です。このサインが見られないときには、子どものコミュニケーションの傾向に目を向けることが大切です。
言葉の遅れ・喃語が少ないケース
言葉の発達もまた、発達障害のサインのひとつとして挙げられることがあります。「1歳半なのに意味のある言葉が出ない」「赤ちゃん言葉(喃語)があまり聞こえない」といった場合には、保護者の方の中にも不安を感じる方がいらっしゃるかもしれません。
言葉の遅れにはさまざまな要因が考えられます。たとえば、
- 聴力の問題
- 環境要因(話しかけの機会が少ないなど)
- 発達の特性
などです。中には、言葉は遅れているけれど、身ぶりや目線でしっかりとやりとりができる子もいます。逆に、表情やしぐさでのやりとりも少ない場合は、より注意深く観察していく必要があるかもしれません。
「言葉が遅い」という一点だけで判断せず、全体的なコミュニケーションの様子を見ていくことが大切です。
一人遊びが多い・感覚過敏のサイン
1歳半くらいの子どもは、大人や他の子どもと関わりながら遊ぶようになります。でも、中には「一人で同じ遊びばかりを繰り返す」「周囲に無関心な様子が続く」といった子もいます。
こうした行動は、発達障害の特徴として知られる「こだわりの強さ」や「対人関係の困難さ」とつながる場合もあります。また、特定の音や光、触感に対して強い反応を示すなどの感覚過敏も見られることがあります。
たとえば、
- 服のタグや靴下を極端に嫌がる
- 電車や掃除機など大きな音に驚いて泣く
- 逆に、痛みや寒さに鈍感に見える
こうした様子は、感覚処理の特性として捉えることができます。
ただし、これらの行動があるからといって、すぐに診断やラベルをつけることは避けましょう。大切なのは、子どもの行動の背景にある「感じ方」や「伝え方の特徴」を理解しようとする姿勢です。
3. 見極めが難しい“個性”との違い
発達の個性と障害の違いをどう考えるか
子どもの成長には、さまざまな「個性」があります。たとえば、慎重な子もいれば、活発な子もいます。ひとつの遊びに集中する子もいれば、いろいろなものに目移りする子もいます。そうした違いは、「その子らしさ」として自然なことです。
しかし時に、「この子の特徴は個性?それとも発達障害なの?」と迷う場面もあるかもしれません。たとえば、言葉が遅い、周囲とあまり関わらない、感覚が過敏…こうした様子がある場合、発達の特性として専門的なサポートが必要なケースもあります。
違いを見極めるひとつの視点として、日常生活の中で困りごとが生じているかどうかがあります。たとえば、保育園や家庭内で「集団生活になじめない」「意思疎通が極端に難しい」といった場合は、支援の必要性があるかもしれません。
つまり、発達の特性は「できる・できない」ではなく、「生活のしづらさにつながっているかどうか」で判断されることが多いのです。
よくある誤解と保護者の不安との向き合い方
「まだ1歳半だから様子を見た方がいい」「男の子は言葉が遅いから大丈夫」といった言葉を耳にすることはありませんか?もちろん、そうした傾向があるのも事実です。でも、それだけで安心せず、目の前の子どもの様子に目を向けることが大切です。
「何か違うかも」という保護者や家族、先生の直感は、とても大切なサインです。子どもと毎日過ごしている保護者だからこそ気づける微細な変化や違和感があります。それを「気のせい」で終わらせず、専門家に相談する勇気を持つことが、お子さまの未来を支える一歩になります。
また、「うちの子が障害かもしれない」と思うと、不安や戸惑いが強くなるのも当然です。でも、もしそうであっても、早く気づくことでできる支援がたくさんあります。早期に適切な関わりを始めることで、子どもの可能性が広がることもあるのです。
兄弟姉妹との比較に注意しよう
同じ親から生まれても、子どもたちは本当にそれぞれ違います。上の子がよくしゃべったからといって、下の子も同じように話すとは限りません。兄弟姉妹で比べてしまうと、「なんでこの子だけ…」という思いにとらわれてしまうことがあります。
けれども、発達のスピードも関心のあることも、子どもそれぞれにペースがあります。比べるのではなく、「この子は今、何が楽しいのか」「どんなことが得意なのか」に目を向けることで、お子さまの成長に寄り添う関わり方ができるようになります。
4. 気づいたときの行動と相談先
まずは家庭でできるサポート方法
もしも気になるサインがあった場合、まず家庭でできることから始めてみましょう。特別なことではなく、日常の中での「関わり方」がとても大切です。
- 名前を呼んで目が合ったら笑顔で返す
- 指さしを促すような遊び(絵本や「どっちかな?」遊び)
- 「できたね!」「うれしいね!」と気持ちを言葉にして伝える
こうした関わりを通じて、子どもは「人と一緒にいるのって楽しいな」と感じるようになります。この「安心できる関係」の中で、少しずつコミュニケーションの力が育っていくのです。
市区町村・保健センターでの相談方法
発達のことで悩んだとき、最初の相談窓口として頼りになるのが市区町村の保健センターです。地域の保健師さんや育児相談員さんが、子どもの発達の相談に乗ってくれます。
特に、1歳半健診のフォローや、「気になる様子が続いている」といった相談にも対応してくれるため、「病院に行くのはまだ早いかも…」と感じるときにも気軽に利用できます。
電話や窓口で予約をすれば、無料で相談できる場合がほとんどです。また、必要に応じて専門機関や医療機関の紹介を受けることもできます。
児童発達支援や専門機関の活用法
さらに必要な場合には、児童発達支援センターや、療育施設、幼児教室、医療機関などが連携し、より専門的なサポートが受けられます。近年では、民間の療育支援教室も増えており、個別支援プログラムを提供するところもあります。
こうした機関では、
- 言語訓練や対人スキルを育てる支援
- 保護者への育児アドバイス
- 医師による発達検査・診断
などが行われており、お子さまの特性に応じたきめ細かな支援が期待できます。特に早期の段階でつながっておくと、就園・就学など次のステップへスムーズにつなげやすくなります。
5. まとめ:早期の気づきが安心につながる
サインに気づく力は保護者の観察力
子どもの発達において、最初の“気づき”を得られるのは、そばにいる保護者の存在です。
「最近あまりしゃべらないな」「呼んでも振り向かないかも」「指さしが見られない」―そんな些細な違和感こそが、大切なサインです。
このような直感は、日々の関わりの中で築かれた信頼や愛情の証です。専門家よりも早く、保護者だからこそ気づける小さな変化を大切にしてください。
早期の気づきは、早めの支援や見守りにつながる大きな一歩です。
見過ごさないこと、そして「心配すること」は決して過保護ではなく、お子さんの未来を守る力になります。
個性と向き合いながら成長を見守る
すべての子どもに、それぞれのペースや表現の仕方があります。
「同じ月齢の子と比べると…」と感じることがあっても、それは決して劣っているわけではありません。
大切なのは、「まだできない」ことばかりを数えるのではなく、「今できていること」や「これから育っていく力」に目を向ける視点です。
発達に特性があることは、その子が生まれ持ったスタイルのひとつです。適切な支援があれば、子どもは自分のペースで、のびやかに可能性を広げていくことができます。
そして、周囲がその子の“やり方”を理解してあげることで、自己肯定感や「自分らしさ」を大切にできる未来につながっていきます。
迷ったときは専門家に相談することが大切
「どうしたらいいか分からない」「気になるけれど誰にも言えない」そんなときは、一人で悩みを抱え込まなくて大丈夫です。
全国には、子どもの発達について相談できる窓口がいくつもあります。
- 市区町村の保健センター(1歳半健診・3歳児健診など)
- 児童発達支援センターや療育機関
- 地域の子育て支援拠点や発達相談室
- 発達に理解のある小児科・医療機関
これらの専門機関では、発達に詳しいスタッフが、今のお子さんの様子を丁寧に見て、必要なサポートやアドバイスを提案してくれます。
相談すること=診断やラベルをつけられることではありません。「安心のための一歩」として、ぜひ気軽に声をかけてみてください。
子どもの育ちは、まっすぐな道ではなく、それぞれの道があります。今の不安は、決して悪いものではありません。気づいたそのときこそが、次の一歩を踏み出すチャンスです
「この子にとって、何が一番心地よいだろう?」
そんな問いを大切に、迷いながらも寄り添っていく日々こそが、最高の子育てです。
今日の「気づき」が、明日の「安心」につながりますように。